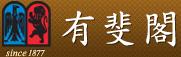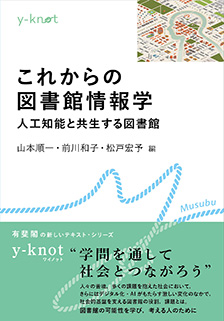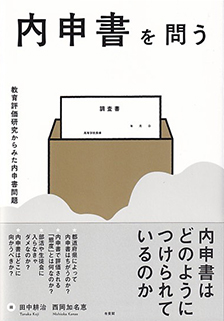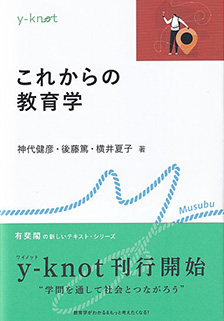Total 8
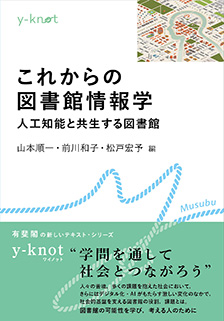 |
 |
y-knot > Musubu
図書館は社会基盤の1つである――図書館の可能性を学び考える人のために
山本 順一 (フリーランスの研究者,著述家),前川 和子 (前大手前大学教授),松戸 宏予 (佛教大学教授)/編
四六判 ,
290ページ
定価 2,200円(本体 2,000円)
ISBN 978-4-641-20017-3
|
 |
人々の苦境・多くの社会課題と,デジタル社会に向けた大きな変化のなかで,図書館に課せられた役割とは。社会基盤の1つとしての公共図書館の機能・課題を整理し,先進事例も多数紹介。新しい時代・社会における図書館の可能性を学び,考えるためのテキスト。
|
 |
○在庫あり
|
2025年04月
 |
 |
有斐閣ストゥディア
子どもについて考える人の必読書
元森 絵里子 (明治学院大学教授)/著
A5判 ,
250ページ
定価 2,420円(本体 2,200円)
ISBN 978-4-641-15135-2
|
 |
「子ども」に関する私たちの常識はどこからきたのか? 欧米と日本の近代化に沿い,保護され教育される存在へと変わりゆく過程を解説。多様な現実や,議論の変遷を社会学の視点で掘り下げ,子どもにまつわる政策論や実践を背景から読み解く力を身につける。
|
 |
○在庫あり
|
2024年12月
 |
 |
有斐閣アルマ > Interest
めまぐるしい時代における図書館の役割を問い直す好評テキストの最新版
山本 順一 (前桃山学院大学教授)/編
四六判 ,
252ページ
定価 1,980円(本体 1,800円)
ISBN 978-4-641-22239-7
|
 |
図書館の役割と制度を理念から平易にコンパクトに解説したスタンダードテキスト【司書課程カリキュラム対応】。最新動向を踏まえ統計データ等を刷新。「著作権問題」「コロナ禍が図書館にもたらした影響」等,近年のホットトピックについても加筆。
やさしい入門書
|
 |
○在庫あり
|
 |
 |
有斐閣アルマ > Interest
累計2万7000部!令和の学校改革/協働的な学びと個別最適化等,近年の動向をふまえ刷新。
田中 耕治 (佛教大学教授,京都大学名誉教授),鶴田 清司 (都留文科大学名誉教授),橋本 美保 (東京学芸大学教授),藤村 宣之 (東京大学教授)/著
四六判 ,
328ページ
定価 2,090円(本体 1,900円)
ISBN 978-4-641-22237-3
|
 |
累計2万7000部の好評書の最新版。方法の歴史と理論を体系的に整理し,わかりやすくコンパクトに解説した入門テキスト。令和の日本型学校教育/協働的な学びと個別最適化/深い学びとICT活用/GIGAスクール構想等近年の文科省答申や社会的動向もふまえて刷新。
やさしい入門書
|
 |
○在庫あり
|
2024年07月
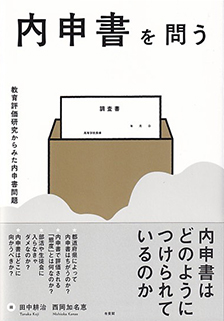 |
 |
内申書をめぐる不安や疑念の在りかに迫る
田中 耕治 (京都大学名誉教授,佛教大学客員教授),西岡 加名恵 (京都大学教授)/編
四六判 ,
260ページ
定価 2,970円(本体 2,700円)
ISBN 978-4-641-17497-9
|
 |
内申書にまつわる問題の所在を明らかにし,教育評価研究の視角から,評価制度はどうあるべきかを探究する。試験一発勝負ではない評価のメリットとは? 内申書はどのように改革すればよいのか? 子どもや保護者,現場の教育関係者や研究者の疑問にこたえる書。
個別テーマの解説書
|
 |
○在庫あり
|
2024年03月
 |
 |
有斐閣アルマ > Interest
教師をめざす,すべての人へ
秋田 喜代美 (学習院大学教授,東京大学名誉教授),佐藤 学 (東京大学名誉教授,北京師範大学客員教授)/編著
四六判 ,
300ページ
定価 2,090円(本体 1,900円)
ISBN 978-4-641-22233-5
|
 |
具体的な教師の姿を通して,教職の理念や基本概念をわかりやすく論じた教職の定番テキスト。令和の日本型学校教育/働き方改革/ジェンダー問題等,コロナ禍を経た近年の動向を盛り込んだ最新版!新規Columnを追加し,内外の統計データを集約した巻末の資料も刷新。
やさしい入門書
|
 |
○在庫あり
|
2023年12月
 |
 |
有斐閣アルマ > Interest
歴史・思想・政策・実践という多角的視点から学べる定番テキスト,最新動向に対応
田中 耕治 (佛教大学客員教授,京都大学名誉教授),水原 克敏 (東北大学名誉教授),三石 初雄 (東京学芸大学名誉教授),西岡 加名恵 (京都大学教授)/著
四六判 ,
378ページ
定価 2,200円(本体 2,000円)
ISBN 978-4-641-22228-1
|
 |
学習指導要領/高大接続改革/コンピテンシー/研究開発学校,教育課程特例校/SDGs/デジタル・シティズンシップ/アファーマティブ・アクション/災害後の教育現場/「生きる」教育など,日本ならびに諸外国の最新動向をふまえて改訂!【教職課程対応】
やさしい入門書
|
 |
○在庫あり
|
2023年09月
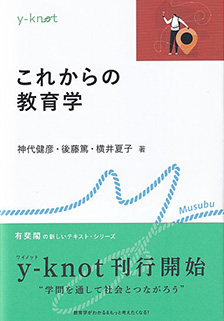 |
 |
y-knot > Musubu
ようこそ教育学へ
神代 健彦 (京都教育大学准教授),後藤 篤 (宮城大学准教授),横井 夏子 (作新学院大学女子短期大学部講師)/著
四六判 ,
262ページ
定価 2,090円(本体 1,900円)
ISBN 978-4-641-20006-7
|
 |
教育学がわかる&もっと考えたくなる!講義→問いの構成で,初学者にも学びやすいテキスト。講義で学んだ理論や概念をふまえつつ,現代社会が抱える課題に,問いを立て,探究する「教育学的思考」を促します。学修をサポートするツールも充実。(教職コアカリ準拠)
<
入門書・概説書
|
 |
○在庫あり
|

|
 |
|