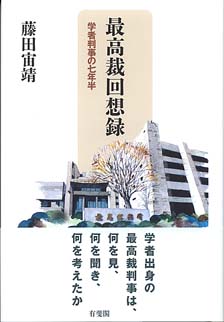| 藤田宙靖[著]『最高裁回想録―学者判事の七年半』<2012年4月刊>(評者:東京大学 長谷部恭男教授)=『書斎の窓』2012年7・8月号に掲載= | 更新日:2012年7月13日 |
1 学者と実務家の間
評者が初めて遭遇した藤田宙靖教授の著書は、 1978年に刊行された論文集 『行政法学の思考形式』(木鐸社刊)である。同書の「あとがきに代えて―行政法学と私」と題された文章の末尾で、若き藤田教授は次のように述懐する。
多くの行政法研究者の強靱なる精神は、私にとって全くの驚異である。何が現社会の真実であり、何が現に存する法であるか、について、どうすれば真に確実な認 識が得られるのか、というような迂遠な問題に悩まされることなく、あるべき“公益と私益の調和”につき、次々と積極的な提言をされるその勇敢さは、私のよ うな者には到底及びもつかぬことである。これらの勇猛な精神に対しては、心からの感服と羨望を禁じ得ぬと共に、ただ、もし私にそのような強靱さがあったな らば、私は恐らくは研究者に非ずして、政治家か行政官か、あるいは法曹になっていたであろうと思うのである。
著名な政治家を親族に輩出する藤田教授にとって、行政官はもちろん、政治家となる途も十分考えられた。しかし、彼はあえて、「公益と私益の調整を最も技術的 なレヴェルにおいて図る」行政法学の素養を身につけようとした。それなくしては、公益とは何か、公益と私益との調整はいかにあるべきかという「本来の問題 について、真に自信を持った主張は出来ない」、と彼には思われたからである。理論法学の極北を摩する藤田行政法学が、その後構築されていく。
この論文集の刊行からほぼ四半世紀を経た2002年7月24日夜、最高裁事務総局人事局長から藤田教授の東京の宿泊先に電話が入る。そして、9月30日、藤田教授は最高裁判事に就任した。
本書では、7年 半にわたる最高裁判事の経験が、裁判官としての執務と生活の実態、関与した事件を通して見た判例の動向、さらには、裁判実務と学説との関係等の論点を中心 に執筆されている。巻末には、著者が関与した事件の個別意見がまとめられているが、これらの個別意見のそれぞれについて解説や感想が付されるという執筆の スタイルは採られておらず、著者の在任中、最高裁が直面したさまざまな問題とそれへの対応を概観し論ずる中で、これら個別の意見も必要に応じて言及されて いる。
2 最高裁判事の選任
著者は自身が「実定法嫌い」であることを公言する(15頁。以下、断らない限り、本書の頁数を示す)。これは実定法解釈学者の「強靱さ」への違和感を示す著者特有の表現であって、実定法解釈学が不得意であることを意味するわけではない。著者が最高裁判事として選任された理由の一つは、著者も認める通り(16頁)、 「専攻分野が行政法であったこと」、さらにその背景として、最高裁における行政事件の持つ重みがあったことは想像に難くない。当事者訴訟の活用、原告適格 の拡大や処分性の拡大等、行政事件の分野で近年の最高裁が示した積極的傾向につき、「行政法学者である藤田がいたからこそ最高裁はここまで来た」との見方 について、著者は「必ずしもそうではな」いとするが(83頁)、謙遜を差し引くとしても、著者の存在という触媒を経て現在の「活性化」がもたらされる程度の素地は、最高裁にもともとあったのであろう。
他方で、就任時期が60歳を超えていた点につき、より若い最高裁判事が任命されないのは、「長年の政権党であった自民党が最高裁判事の政治的傾向を自分らのそれと同一に保つことができるようにするため」という学界の一部の見方に対して、著者は否定的である(16頁)。裁判官出身の判事が、いわばキャリアの最後の到達点であり、定年の65歳直前に就任するのが例であるため、それと極端には異ならない人事が他分野出身の判事についても行われているにすぎない。
最高裁の判断が一般的に言って「保守的」であるとの安易な評言についても、著者は、民事・労働分野における従前からの最高裁の積極的判例形成を軽視してい ることに加えて、憲法事件についても、裁判所の任務の核心が奈辺にあるかを知らぬ物言いではないかとの疑念を提起する(121頁)。
3 裁判所の任務
著者が繰り返し強調するのは、裁判官の第一義的な任務は、「目の前にある当事者の現実の争いについて、そのいずれかに軍配を挙げること」であり、そして、その場合の判断の基準は、「一重に『適正な紛争解決』であるかどうか」であることである(136頁)。法律の解釈も「最も適正な紛争解決」を目指す判断過程の中での作業にとどまるし、「憲法の規定や法の一般原則が引き合いに出されるのも」「あくまでも、目の前の具体的な事件について『最も適正な解決』をもたらすための一手段」としてである(138頁)。
裁判所は一般的な法解釈理論の構築を目指しているわけではなく、また、憲法価値の実現自体を目的とするわけでもない。裁判は、「目の前にある個別的事件の事実関係を前提として、その紛争をどう解決するのが最も適切かという見地からなされる」(145頁)。法理論ではなく、むしろ具体的な事件に関する判断の積み重ねである判例が、裁判所の参照すべき第一の手がかりとなるのも、そのためである(154頁)。
憲法を頂点とするピラミッド型法秩序観やモンテスキュー流の三段論法型司法観で頭が一杯になった法律学者はとかく忘れがちであるが、日本語で「司法」とされるのは、英語で言えばJusticeである。正義、それも個別の紛争に際して、各当事者に正当なものを割り当て、配分する具体的正義の実現が、裁判の任務である。著者の指摘は、アリストテレスの司法観(『ニコマコス倫理学』第5巻第10章)にも遡り得る裁判のそもそもの任務、さらには法律を典型とする「法」の役割とは何かという論点を思い起こさせる。
アリストテレスによれば(プラトンによっても)、裁判の目的は前に述べた具体的正義の実現である。優れた裁判官が個別具体の事情に即した適切な解決を下す ことが最も望ましい。しかし、優れた裁判官はいつもそこにいるわけではない。このため、似通った大部分の事例で程よい解決を示す一般的な実定法による裁判 の拘束が必要となる。法に基づく裁判は、次善の手段である。下級審の裁判であれば、安全策をとって、実定法通りに裁判をすることで事足りるかも知れない。 それで、大部分の事案では程よい解決が得られる。しかし、最高裁まで争われる事件の中には、法が一般的に指示する解決が、当該事案の個性に即した適切な解 決とならないものもある。適切な解決を求めて法の解釈、ときには憲法や法の一般原則に基づく実定法の適用の排除がなされるのは、そうした場面である。
では、「適切な解決」は何に基づいて判断されるのか。著者が指し示しているのは、各裁判官の「良識」であり「良心」である。それは、「必ずしも法律学説や法理論であるわけでは」ない(122頁)。あまりにもまっとうな常識論であり、それを超える手がかりは無いのか、との感想もあるかも知れないが、評者の見るところ、それを超えるものは探しても無い。
人として何をなすべきか、目の前の問題をいかに解決すべきか。こうした実践理性の諸問題は、各人がその良識に基づいて答えを出すしかない。法は、実践理性 の判断を簡易化し、標準化する道具にはなる。しかし、それはあくまで次善の手段である。事案に即した「適切な解決」が実定法の指示する回答と合致している か否か、それは最後は人としての裁判官が自己の良識に照らして判断することである。裁判官であることは、人であることをやめること、人としての実践的判断 を止めることではない。
そうした「良識」は時代によって変化しうる。著者は、最高裁判事の中に、第二次大戦終了後に生まれ、戦後の教育を受けた者が増えつつあることを指摘する(122頁)。そして、官僚出身か、それとも民間かといった「レッテル貼り」よりも、世代交代に伴う判例の変化に着目すべきことが示唆される。
4 裁判官の暮らし
本書の滋味は、最高裁判事の執務ぶりや裁判以外の公務、海外出張や宮中との関係等の記述にもあふれている。処理すべき事件数の多さと激務ぶりには、やはり驚かされる。スーツ以外の服装をするには一大決心が必要であるとの経験談は(170頁)、思ったよりは自由であったとはいえ、判事生活の窮屈さをはしなくも示しているし、代沢の裁判官公邸に出没するらしい幽霊(?)の逸話は(22頁)、 今後、最高裁判事に就任する方々にとっては貴重な情報であろう。著者の著作にあまねく見られる仄かなユーモアのセンスが、本書の背景にも流れている。肩に 力が入りがちなテーマが論じられている場面でも、「そう硬くなるほどのことでもない」という著者のアドバイスが聴こえてきそうである。
法律の専門家のみならず、一般の読者にも広く本書をおすすめしたい。
(はせべ・やすお=東京大学法学部教授)