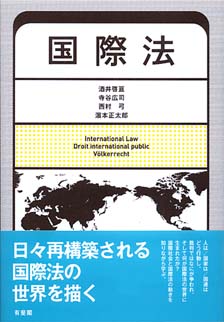| 酒井啓亘・寺谷広司・西村 弓・濵本正太郎[著]『国際法』<2011年12月刊>(評者:名古屋大学 小畑 郁教授)=『書斎の窓』2012年6月号に掲載= | 更新日:2012年6月16日 |
国際社会の大変動と法・法学
私の手元に一冊の本がある。1984年刊の『基本条約・資料集〔第4版〕』(有信堂)全491頁である。この書物を実質的に継承する最新刊の『ベーシック条約集2012』(東信堂)は全1244頁であるから、この28年間の間に大学の法学部で国際法を学修するのに必要な資料の分量は、約2.5倍となったことが分かる。これをカヴァーする国際法の講義コマ数が、良くて現状維持であることを思えば、現代の学生たちの困難は明瞭である。もちろん、年々増している情報量をどうこなすかというのは、国際法学に固有の問題ではない。それに特徴的な困難は、質の上での著しい変化にある。右の二つの資料集の形式的な比較からも、国内法や国連安全保障理事会決議の大幅な採録が観察される。
こうした質的変化は、冷戦の崩壊あるいは冷戦が封じ込めてきた差別的戦争概念の全面展開と関係がある。実際、冷戦期には予想できなかった現象がこの20数年間に生じた。国連の強制措置の復活と頻繁な適用(濫用?)、個人の重大犯罪を国内法上の性質決定の如何にかかわらず処罰する国際刑事裁判所(ICC)の設立、および、地域的なものだが、欧州連合法の憲法秩序化といったものを挙げるだけで十分であろう。これらは、主権的存在たる国家の地位や、こうした国家(のみ)を構成員とする国際社会の原子論的な把握、といった旧来の国際法の基礎概念を、根底から揺さぶる現象と考えなければならない。
国際法の新しい体系を求めて
実のところ、私は、こうした変動をも含めて現段階で国際法を総体として把握するためには、既存の体系は適切ではなくなっていると考えている。戦後日本の国際法学では、基本的には、総論的叙述を置いた後に、権利の主体(国家)―権利の客体(領域と人)―権利の変動(条約法と国家責任法)と続けるパンデクテン体系を踏襲し、さらに紛争の平和的解決、戦争の取扱いと戦時法といった通常の秩序が乱された場合の国際法を議論していくスタイルが、さまざまな現代的装いをまといつつも受け継がれてきた。
私がより問題だと感じるのは、ときどきの問題に関連する個別の国際法規を当てはめて適用すれば済むと言って憚らない態度である。こうした態度は、国際法を過度に物象化しないという効能をも期待されている。しかし、右に見たように、資料情報が爆発的に増大する今日、幹と枝葉とを整理されないままでは、人々は情報の海に飲み込まれ溺れてしまうだろう。その結果生ずるのは、専門家たちが「これがその問題に適用される国際法規で、それはこう解釈すべきです。それを裏付ける資料はこれです」と「教える」ことを鵜呑みにすることであろう。新しい体系が求められるのは、まさにこの事態を防ぐためである。
気鋭の著者による革新的国際法教科書
本書の著者たちは、私より少し若い世代に属し、上の世代が黙って一目置く存在である。彼らが、長年の議論を経て800頁を超える大部の国際法教科書を刊行した。しかも瞥見するところ、さまざまな新機軸が織り込まれている。期待は否が応でも高くなる。本書は、右に述べたような日本の国際法学・教育に対する私の危機意識に応えてくれるだろうか。
実は、本書の特徴は、さまざまな関連諸現象を、これでもかというほど豊富に取り込んでいること、索引を通じて原典(に近い資料)にアクセスできるようにしていることなど、むしろ学習者が生の現象に触れ自ら考えるための工夫が凝らされていることにある、ともいえる。他方、筆者たちは、そうした諸現象をバラバラに提示することを拒否する。「国際社会において、ある制度がどのような論理と意義をもって妥当しているのか、国際法規範全体の中でどのような位置づけを占めるのか」(ⅲ頁)を意識して叙述したという。こうした態度から、「体系」とそれを基礎づける総論の重視が高らかに宣言される。「体系的記述を展開する上で、本書の冒頭(序)において、ここで用いられている概念の整理のほか、国際法の歴史や国際法学の方法論にまで比較的深く言及した。『体系』は単なる並び方の問題なのではなく、そこに内在する論理こそが重要だからである」(ⅰ頁)と。
プロセス志向の体系へ
しかし、本書が提示する体系は、従来の日本の教科書の体系とは全く異なる。「序」―第1編「国際社会の法的構造」―第2編「国際法規範の形成」―第3編「国際社会の空間秩序」―第4編「国際法秩序の維持システム」―第5編「国際公益の追求」(各論的再叙述)という流れは、国際法の論理構造というよりは、「国際法なるもの」がプロセスとしてどのように運動しているか、ということを提示しているのである。これは、たとえば行政法総論を行政過程論で包摂する試みに符合し、規律対象の拡大とアクターの多様化現象を取り込もうとした場合の現代公法学の一つの典型的対応である。つまり、さまざまな形で現れる国際的公権力行使を法的規制体系の中にうまく位置づけられない伝統的ドグマティークに対する、健全で果敢な批判がここに示されているのである。
しかし、そうした構成は、国際法の規範論理構造を把握しようという志向とは、基本的に対立する。総論において、その構造についての理解がこれまでのものとどのように異なるのかがもし示されないとすれば、ただ単に「現象」をその切り取り方の基準を示さないまま過程の中で述べ直したものに過ぎなくなるだろう(第3編の座りの悪さも見よ)。
無規定・コントロール不能の「国際公益」概念
ともあれ、プロセス志向の体系それ自体は、国際法の実体規範の内容について予断を下すものではない。しかし、プロセスの効率性を志向すればするほど、プロセスを動かす動因(追求される法益)としてどのようなものが設定されているかが決定的に重要になる。これについては、第5編で詳述される「経済」「国際環境・共有天然資源」「平和」「人道」「人権」および「国際犯罪の防止」のいずれもが「国際公益」の追求という単一の概念で導かれるものとなっている。さらに、こうした「公益」を含む「法益」の分類と論理的区別には、コミットメントを避ける態度がとられている(6-7頁)。評者も、論理的に立てられうる区別を超えて現象としては流動的であることは承知しているつもりであるが、ここに踏み込むのでなければ、今や理論の存在理由は失われてしまうだろう。「公益」追求の実効性の名の下に、暴走する国際法制度を、私たちは現認しているのである。
「世界の法化+ステイティズム」のプロジェクト?
本書においては、「国際法を実現するための様々な制度を……国際法秩序の維持システムを構成するものとして捉え直し〔た〕」(ⅰ頁)第4編に実に140頁が割かれている(序・第1編は計107頁)。第5編での履行確保の強調と併せてみれば、法秩序の維持そのものをあたかも自己目的的に追求するものとして国際法が描き出されているともいえる。
これは、「責任のすべてを、そして責任だけを」というスローガンの下に、膨大な(実体規範との繋がりを失った)法体系を描いた国際法委員会の国家責任条文作成作業を彷彿させる。私の観察では、その作業では、責任制度が確立しているか怪しい分野への一般化が大規模に行われ、法フェティシズムを満足させることにより結果としてステイティズム的介入の余地が広げられた。本書も、国家を他の国際法主体とは並列に扱うことのできない特権的主体として扱い(39頁参照)、このような「国際社会の構成員」理解と「主権・国家管轄権」で「国際社会の法的構造」(第1編)が構成できるという支配的観念に同意するのであるから、国家責任条文に抱くものと同様の懸念は払拭できない。
「対抗措置」の位置づけをめぐって
もとより筆者たちは論理分析に優れた研究者であり、本書はその反映でもある。とくに国際法規範の形成について瞠目すべき新境地が切り開かれている。さらに、各編の内部構成に立ち入れば、従来の論理構造理解とは異なるものが示されている。たとえば、対抗措置の位置づけがそうである。対抗措置は、国際違法行為の責任国に責任内容を履行するよう促すためにとられる措置(つまり不法結果ではなく責任追及の一つの手段)と今日では解されているが、そうすると、現実にはまだ相手国の責任は確定していないので、それは前提要件とはならないはずである。こうした論理を辿って(cf.375-376頁)、本書は、対抗措置を国際責任ではなく紛争の平和的処理のなかで取り扱うのである。
この論理は鋭い。もっとも、このように位置づけた結果、この概念は、かつて存在した、「容易に国際司法(正義)の運営の歪曲に導きうる」(コルフ海峡事件判決)との批判に耐えられないものとなっているのではないだろうか。だから国際法の支配的言説は、これを責任制度に位置づけ、正義の実現と結びつけて正当化しているのである。こうした支配的言説が抱えている矛盾そのものは、かえって覆い隠されてしまったようにみえる。
神官(教育)のための「学」か、人間が世界を主体的に生きるための学か
いうまでもなく「体系」は自由に構築できるものではなく、国際法についての支配的(諸)言説を踏まえ捉えるものでなければならない。しかし、それでもなお「体系」を語るという営為は、筆者・出版元からして権威性を運命づけられた教科書においてはなおさら、国際法言説の(再)生産という実践的なものにほかならない。そしてもし、人間が世界を主体的に生きるための学として国際法学を位置づけるのであれば、支配的言説(の諸ヴァリエーション)に対する自らの構えは、強く意識されなければならない。
もちろん、その自覚を意図的に隠蔽して「国際法」という名の宗教の正統学説を教化する「学」もあるであろう。しかし、本書の著者たちは、それを目指しているわけではないと私は確信している。「一つの『体系的』認識の提示は、……その時点で認識の枠組みを固定化させてしまう危険をもたらすこともまた、我々は十分に承知している」(ⅲ頁)とも書かれているからである。さらに、「他者の行動に素早く反応して法的見解を示し、自国の行動を周知させ、それを理解しやすく整理して公表する財政的・人的・知的資源を有する国と、そのような資源に欠ける国との間では、慣習法規範形成における現実の影響力に差が生まれてこざるをえない」(150頁、割注略)といった認識は、「国際法なるもの」の批判に開かれた体系構築を目指す私にとっても、重要な礎石の一つである。
(おばた・かおる=名古屋大学大学院法学研究科教授)