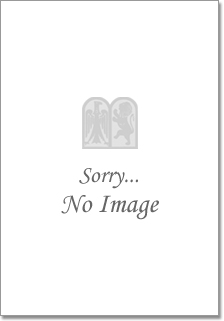| 大東英祐・武田晴人・和田一夫・粕谷 誠[編]『ビジネス・システムの進化』<2007年9月刊>(評者:一橋大学 米倉誠一郎教授)=『書斎の窓』2008年5月号に掲載= | 更新日:2008年11月14日 |
はじめに
経営史研究の主たる対象である企業は,しばしば市場という広大な海に浮かぶ島に譬えられる。市場という海は価格メカニズムという「見えざる手」により支配され,企業という島の経済活動は目的意識的な管理調整機能システム,すなわち「見える手」の下に置かれているという経営学の考え方である。価格メカニズムによる調整よりも管理調整システムによるものの方が効率的である場合にのみ,企業が存在するということになる。しかしながら,現実の企業と市場との境界は,海と島の譬えが示唆するほどには明確ではなく,中間的な領域,いわゆる中間組織があると指摘されてきた。また,どんなに多くの経済機能を内部化した企業といえども,島のように孤立した自己完結した存在でないことも明らかである。企業は他の多くの企業との間にさまざまな関係を保ちつつ活動しているのである。
これらを踏まえて,A・H・コールは,企業者をめぐる経済的・社会的な関係を第一に企業内の組織の形態や構成員との関係,第二に「企業者的な流れ」,すなわちクラスターに近い企業や諸機関との関係の総体,そして第三に多くの人々によって共有されている価値意識とそれに連なる諸制度とに区分している。本書は,コールが区分した三つの次元の経済的・社会的な諸関係の全体を「ビジネス・システム」と定義し,その発展のプロセスを明らかにすることで,経済発展の過程を明らかにすることを目的としているという。
各章の概観
まず第1章では,19世紀アメリカのボストン商人に焦点を当て,中国貿易を中心とする遠隔地貿易による商業的な資本の蓄積とその後の産業投資活動を分析している。当初の中国貿易は積荷の準備,現地での売り捌き,帰り荷の仕入れまでの一切の責任を負うスーパーカーゴ(積荷監督)を大航海ごとに任命するという形で始まった。しかし,船や手紙の往来に片道六カ月もかかるという当時の交通・通信事情を考慮したとき,商機を逃さずに在庫の仕入れや処分を行うためには広範囲な裁量権を保持した責任者が現地に常駐するという,いわゆる「定住商人」というシステムが利用されることとなる。アメリカ鉄道事業のパイオニアの一人として数多くの鉄道計画に関与したT・H・パーキンスは,自ら中国貿易のスーパーカーゴの経験を持つ。そして,ミシガン・セントラル鉄道やシカゴ・バーリントン・クウィンシー鉄道への投資で知られるJ・P・カッシングは,パーキンスのパートナーとして二〇年以上にわたり広東の「定住商人」を務めている。また,ミシガン・セントラル鉄道の買収で知られる鉄道王J・M・フォーブスも「定住商人」として広東に滞在した経験を持つ。ボストン商人による「定住商人」というシステムを利用した中国貿易は,蒸気船への転換の遅れと海底電線網の整備によって,南北戦争後にはその経営ノウハウが急速に陳腐化し,衰退する。しかし,中国貿易を通じて蓄積された彼らの莫大な資本は,新たな産業投資資金の供給源の役割を果たすこととなる。そこには,「伝統的な商業資本から近代的な産業資本へ」という道筋とは異なる進化の系統があったことが示されている。
次に第2章では,20世紀初頭の日本で設立された損害保険会社3社の発起人や出資者に着目することで,明治末期に企業が設立発起される際の基盤・設立母胎について考察している。3つのケースは,まず「資産と名望を有する財界人を起点とした血縁的・地縁的・同業者仲間連鎖を通じて賛成人や株式応募者がたぐり寄せられる」という地域財界の共同出資によるという産業勃興期に典型的なケースである。次に,設立・発起の段階では資本の縁故募集を念頭に置いているが,その出資者を自由で機会主義的な投資家に見出すケースである。最後は,将来の顧客を出資者に想定し,顧客へのサービスと出資からのリターンの両面から「相互社会的な」枠組みを提案することで出資を仰ぐというケースとなる。タイプの異なる事例を検証することで,企業設立に関わる出資者と事業計画との間のミスマッチが産業勃興からの時間経過に応じて減少し,両者を結びつける制度的な枠組みが着実に進化していることが明らかにされている。
続いて第3章では,明治以降の日本における決済ネットワークの発展と金融市場の成長を分析の対象としている。経済発展の前提として,決済の効率性の向上は必須となる。日本における銀行制度は,明治初期に西洋から導入され,手形割引などの決済に関わる仕組みの移植が試みられた。一方で,江戸時代からも大阪を中心に,両替商宛振り手形(小切手類似の証券)という形で,集中決済機能こそないものの高度な金融システムが機能していた。近世の日本においては,為替手形は遠隔地取引には用いられるものの同一地域内の取引にはあまり用いられることがなかった。しかしながら,再割引銀行として設立された日本銀行を媒介とすることで,手形交換という国立銀行による決済機能の中心的インフラとして普及していく。在来的な日本のシステムと合理性を持つ西洋的なシステムとの接合という観点から,明治期日本の金融市場の発展過程を詳細に検証している。
第4章は,昭和初期の電線業のケースを取り上げ,戦間期における日本の企業間関係について考察している。古河財閥による古河電工に対するコンツェルン的な子会社統制の試みと,通信ケーブル分野において古河電工と住友電工がカルテル的な協調関係を築き上げることを通じてその寡占的地位と利益の確保をしていった経過が明らかにされている。社史のみにとどまらず,現存する協議書や申合書,そして訴状などの一次資料を丹念に検証することで,財閥によるコンツェルン的な統制が弛緩する戦間期にあって,カルテル的な調整・統制が機能したこと,また政府による積極的な関与がそれを支えたことが示されている。
第5章は,企業の衰退・破綻に焦点を当てている。20世紀初頭には世界屈指といわれた機械メーカーであったプラット・ブラザーズ社は,豊田自動織機製作所から自動織機の特許を譲り受けたことから日本でもよく知られる企業でもある。少なくとも第2次世界大戦前までは世界屈指の繊維機械メーカーであり,プラット・ブラザーズ社単独の生産量はアメリカの繊維機械の全生産量に匹敵するほどの企業であった。しかしながら,需要が衰退し,市場が縮小する中で,同社は供給を制限するという方法で競争の抑制の方向へと舵を切ることで状況に対応する。余裕資金に関しても,それを製品の製造方法の抜本的見直しや製品構成の再編,経営の多角化のために投資するのではなく,同業他社を買収するために振り向けていった。同社の競争抑制策は,その後国際的なカルテル形成にまで及ぶが,最後には多額の買収資金の利子負担に耐えられず,破産することとなる。地理的に見れば世界的な規模での拡大であっても,縮小する市場の中で同一セクターの事業に固執することで,企業自身が衰退・破綻への道を歩むことになるという典型例が描き出されている。
そして,最後の第6章が評者にとっては最も面白く痛快であった。『フォード・システムの再検討』と題して,大量生産システムの代名詞ともなっているフォード社のハイランド・パーク工場の位置づけを再検討したこの章は,「コンベアーの導入が組立時間を約八分の一にまで短縮し,コストを大幅に削減した」という一見常識となった感のある教科書的記述を徹底検証する。その槍玉に挙げられるのが評者の『経営革命の構造』のフォードに関する記述である。評者の記述から参考としたであろう著作を特定し,その著作のベースとなった資料をさらに特定してその曖昧性を明らかにしていく。この過程は,まるで推理小説のようでかなりゾクゾクさせられた。そして,いまやその根拠も明確でないままに繰り返し引用される「八分の一」という時間短縮の意義と,移動式組立法の導入と大量生産の因果関係について強い疑問を差し挟むのである。まず,「八分の一」という観察事実とコスト削減については,ベルトコンベアーという生産革新に加えて,同時期に実施された日給の大幅な増額が労働者に与えた影響を考慮する必要性が訴えられる。確かに,最近のセル生産方式の成功が明らかにするように,労働者の主体的モチベーションが生産性向上に果たす役割は機械化以上の効果がある。さらに,フォード社が年産二〇〇万台という大量生産を可能としたのは,ハイランド・パーク工場への移動式組立法の導入だけが唯一の要因なのではなく,当該工場が全米各地でノックダウン生産を展開する分工場に対する部品製造基地として機能したためという。すなわち,より広範なビジネス・システム的な視点が強調されるのである。この章の丹念な分析が明らかにしたことは,歴史家が真剣な資料調査や問題意識を置き去りに,過去の引用を孫引きする危険性や,一事例をもとに全体像を見失う危険性なのである。自戒。
おわりに
さて,システムとは「複数の要素が有機的に関係しあい,全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体」(『広辞苑』)を指す言葉である。『ビジネス・システムの進化』という本書のタイトルは,経営史を研究する者にとってはきわめて魅力的なものである。しかも,当代一流の経営史研究者たちの手による本書は,既存研究の丁寧なレヴューとそれを鵜呑みにしない仮説,丹念な一次資料の考証,そして精緻な論理構成と,さすがに読み応えのある論文集でもある。しかしながら,敢えて論文集と表現する理由は,この著作にシステム的統合感がないからである。挑戦的なタイトルと一流の執筆陣とに対する期待が大き過ぎたためか,著者たちは「ビジネス・システム」という言葉に共通の定義を与えようと真剣にブレイン・ストーミングしたのだろうかという疑問が残る。定義が緩やかにされたことで,論文集としての幅が広がったとは思うが,是非とも「ビジネス・システム」という新しい言葉の定義にタックルすることで,経営史研究における新たな視座を提供してくれることを期待したい。
(よねくら・せいいちろう=一橋大学イノベーション研究センター教授)