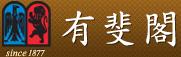自著を語る
『教育格差の社会学』を上梓して
お茶の水女子大学理事・副学長(教授) 耳塚寛明〔Mimizuka Hiroaki〕
「教育格差」という言葉を冠した本が何冊もある。新聞の見出しにも教育格差が踊る。かのWikipediaにも教育格差という項目がある。しかし教育格差は学術的な専門用語ではない。きちんとした定義はなく、また人々がこの言葉に込める含意やこの言葉から受け取る内実は多様だろう。流行語だといったほうがよい。にもかかわらずなぜ、あえて手垢の付いた「教育格差」を主題に据えたのか。答えは「だからこそ」である。あいまいな「教育格差」で括られる現象は、子どもたちの学力格差、高等教育機会と就職(学校から職業への移行)における格差、非行や犯罪を生み出す社会構造、ジェンダー、福祉などの多様な視角を備えなければならない。格差が生み出されるメカニズムを現象ごとに理解したとき、教育というごく限られた領域の背後にマクロな現代社会の統合的な実像が見えるようになるであろう。
この本は、有斐閣のアルマシリーズの中で、いわば「専門科目」に相当する教科書である。ただし、本書を編むに際して、“教科書” ではない「教科書」を作ろうと思った。そこには大学という風景の中で私が主観的にため込んできたいくつかの思いを込めた。
「聖書」のように読む
“教科書”に書かれているのは、専門家たちによってすでに評価の定まった体系的知識である。だから読者すなわち学習者は、その知識の正当性を前提としてこれを受容的に理解して自らのものとするのがふつうである。“教科書”の世界では、“教科書”に書かれた“真実”を前にして、頭脳にこれを素早く吸収し、できるだけ多く蓄えるのが、よき“学習者”にほかならない。
私の勤務する大学の初年次演習でしばしば見られるのは次のような風景である。初めてゼミの発表をする学生は、指定されたテキストを一所懸命読んで無心にレジュメを作成し、正しく明快に要約できる。好ましい。けれども致命的に欠けているのが文献に対する批判的構えである。論者の立場に立ってまずは素直に論旨を読み取る。それは読むことに不可欠なのだが同時に第1歩に過ぎない。そこで終わってしまえば論旨を「聖書」のように受け入れるしかない。事実誤認、論理の飛躍、前提の不確かさ、根拠薄弱、データ解析の誤謬、過度の一般化など、論者が犯したかもしれない過ちは一顧だにされないまま、結論だけが、うぶで吸収力に富む真綿のような頭脳に染み入ってしまう。だから討議の段になると大方は寡黙な人に化してしまう。論者と異なる結論を引き出すための論理回路と構えが排除されてしまっているので、そもそも議論が成立しない。聖書のように読んで吸収してしまう素直さは、結果として「長いものに巻かれる」ことにつながる。知的無垢さは、権力や権威が提示する歪んだ世界観をも抵抗なく受容して、容易に時代の加害者に化けてしまう。これが“教科書”とよき“学習者”の世界である。
知識の生産者への変身を促す
この「教科書」が想定しているのはそのような“学習者”ではない。“教科書”に書かれた知識は、神が与えたもうたかのように私たちの前にアプリオリに存在するものではまるでない。知識は、何者かが、この世界をある方法によって観察して切り取って整序した「事実」ないしは「世界観」に過ぎず、 “真実”ではない。観察者が異なれば、観察する方法論が異なれば、そして事実の組み合わせ方(整序)が異なれば、そこには違った世界が見えてくる。だからこの「教科書」が望むよき「学習者」とは、知識の受容者ではなく知識の生産者たらんと欲する自律的な「学習者」である。「学習者」は従順で受容的な“学習者”と比べて、じつに疑り深く扱いにくいはずである。この「教科書」が育ってほしいと願っているのはそういう「学習者」である。知識を正しく理解できる能力を持った上に、自ら新しい知識を生産することのできる「学習者」である。
知識受容的な“学習者”から知識を自ら生産する「学習者」への変身を促すために、この「教科書」では、各領域における教育格差について課題、分析と提言を述べた本文部分に加えて、何種類かのコラムを設けることにした。「知識生産のための方法論」は“学習者”から「学習者」への変身を直接促すための解説である。自律的な「学習者」には同時に課題解決の方途を考案する力や、それに必要なツールを身につけてほしいと思う。「政策・施策の動向」はそれに資するよう設けた。「Problem Thinking」に上げられた問いを前にして途方に暮れる学生や読者がいるかもしれない。もとより答えが容易に出ない問いを投げかけるコラムであるので、むしろ途方に暮れることを期待した。大方の問いには、人生における問いと同様に、唯一の正答などないからである。このほか読者のさらなる学習のガイドとして「Further Research」を、重要概念について解説する「Keywords」を設けた。
こうしたコラム設定の工夫をしたからといって「学習者」への変身が容易に可能となるわけではない。試しに私自身がゼミで本書を使ってみた。報告者には「Problem Thinking」への回答も求めた。先述の通り、答えの出にくい問いを前にして現象を記述し、概念を使って分析し、自分なりに思考してもらう練習問題のつもりである。ところが“学習者”は素頭で考える代わりに専門書渉猟の遠い旅に出かけて、答えを持参して帰ってきてしまった。調べ尽くすことは実社会でも美徳であって否定されるべきではない。頭を抱えた。答えがそうそう転がってはいない問いに差し替えねばならない。改訂時の課題である。
現代社会に生きる人間として
知識生産者への誘いや研究方法論の強調は、じつのところ諸刃の剣であるかもしれない。大方の大学卒業生が、とくに文系学部の出身者が研究者になるわけではないのだから、研究者と同水準の方法論への理解が必要だとは思われない。しかし知識への懐疑的な構えや多様な分析・解釈の可能性への認識を高等教育人材が身につけていないとすれば、その社会の将来は暗い。だからこのテキストの狙いは基本的に間違ったものではないと思う。しかし知識生産者への誘いや研究方法論の強調は、それだけが1人歩きしたり至上主義扱いされるべきものではない。その陥穽が表れやすいのは大学院生や若手研究者ではないか。本書が想定している主たる読者には彼らは含まれないが、知識生産の過程に潜む危険がまずもって彼らを襲いやすい。
私が属する学会を例にとれば、学会報告を聞いても刺激的な研究発表に出会うことが乏しくなった。もちろん情報の受け手が年をとったためだがそれだけではない。教育界は激しく動いている。にもかかわらず、教育政策や教育変動を見据え、その再検討を迫るような研究はごく少ない。研究が持っているはずの社会的インプリケーションを読み取れない研究が多い。教育学界は批判精神を希薄化させ、時代から切り離された研究世界へと自閉していくように見える。研究成果はまずもって学問上の発見の観点から評価される。新しい研究方法も注目を浴びる。正しい。そのために研究者――とりわけ大学院生や若手研究者は、研究者から高い評価を勝ち取ることを目指して学び成果を発表する。こうした、研究者になるための、またすぐれた研究者として評価されるための合理的行動の中に、学界が時代から切り離され自閉していく仕組みがビルトインされている。学部学生のような学習者も同じ仕組みの中に放り込まれてしまう。なんのための教育研究か。だれに向けて研究成果を発表しなければならないのか。時代を読み解き、時代と闘う構えこそが社会科学者としての生命線だと思う。
教育格差はさまざまな格差の中で、“The 格差”として注目されるべき重要性を持つ。それは、親世代の格差が子世代へと再生産され、人生のスタートラインにおいて機会が平等に開かれているわけではないことを端的に示すからである。読者には、さまざまな教育格差が生み出されるメカニズムに触れ、格差を克服するための諸施策の有効性や脆弱さを知ってほしい。そして現代社会の行方を、自ら、選択してほしい。
本書は私だけの作品ではない。私は編んだだけで7人の共著者の社会科学的な営みの産物である。国立大学法人の管理職へと